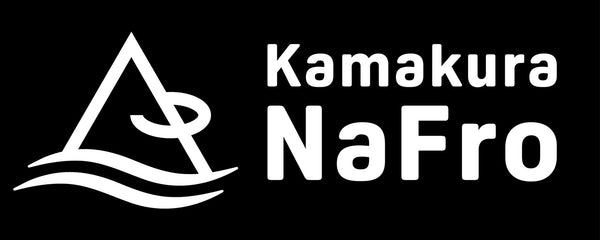Journal

ソロキャンパーにおすすめ!料理初心者でも簡単「キャンプめし」
こんにちは! キャンプD2CのNaFroです。 「外で食べる料理はおいしい」とよく聞きます。焚火や炭火で作る香ばしく味わい深い「キャンプめし」の数々。自らの手で火をおこし、料理の下準備をして、調理するのもキャンプの醍醐味です。 自然の中で遊んだ後の空腹感や、気持ちのいい風もスパイスとなり、より一層おいしく感じることでしょう。この記事では魅力いっぱいの「キャンプめし」をご紹介します。 2024/03/04 更新 無理のない食事プランを立てよう! 折角のキャンプだからと気合の入った食事プランを立ててしまうとキャンプの間中、調理に時間をとられて1日が終わってしまうこともあります。焚火や遊びの時間も有意義に過ごすために無理のない食事プランを立てましょう。 キャンプだからといってすべて手作りである必要はないので、サイドメニューは出来合いのものを買ってしまうのも良いでしょう。 自宅の冷蔵庫を見て余った食材を活用しよう 余った食材で冷蔵庫がいっぱいになった経験はありませんか?食事プランを立てたら使用する食材をリストアップしてみましょう。 そうすることで大量に買い込んでしまうことも防げます。また、必要な食材だけ購入することで、荷物も少なくなりコスト削減も期待できて一石二鳥です。 おすすめ「キャンプめし」 コーラでコクが出る「コーラチキン煮込み」 【材料/1人前】 ・鶏もも肉 100g ・ショウガ 1片 ・ニンニク 1片 ・鷹の爪 1本 ・コーラ 70cc ・オリーブオイル(サラダ油でも大丈夫です。) 大さじ1 ・コショウ 適量 ・塩 適量 ・水 1/2カップ ・じゃがいも 1個 ・にんじん 1本 1.じゃがいもとにんじんは皮をむき、乱切りにしておく。 2.鶏もも肉を開いて軽く塩とコショウをまぶしておく。 3.ニンニクとショウガの皮をむき、薄くスライスし、鷹の爪は刻んで種を取り除いておく。...
ソロキャンパーにおすすめ!料理初心者でも簡単「キャンプめし」
こんにちは! キャンプD2CのNaFroです。 「外で食べる料理はおいしい」とよく聞きます。焚火や炭火で作る香ばしく味わい深い「キャンプめし」の数々。自らの手で火をおこし、料理の下準備をして、調理するのもキャンプの醍醐味です。 自然の中で遊んだ後の空腹感や、気持ちのいい風もスパイスとなり、より一層おいしく感じることでしょう。この記事では魅力いっぱいの「キャンプめし」をご紹介します。 2024/03/04 更新 無理のない食事プランを立てよう! 折角のキャンプだからと気合の入った食事プランを立ててしまうとキャンプの間中、調理に時間をとられて1日が終わってしまうこともあります。焚火や遊びの時間も有意義に過ごすために無理のない食事プランを立てましょう。 キャンプだからといってすべて手作りである必要はないので、サイドメニューは出来合いのものを買ってしまうのも良いでしょう。 自宅の冷蔵庫を見て余った食材を活用しよう 余った食材で冷蔵庫がいっぱいになった経験はありませんか?食事プランを立てたら使用する食材をリストアップしてみましょう。 そうすることで大量に買い込んでしまうことも防げます。また、必要な食材だけ購入することで、荷物も少なくなりコスト削減も期待できて一石二鳥です。 おすすめ「キャンプめし」 コーラでコクが出る「コーラチキン煮込み」 【材料/1人前】 ・鶏もも肉 100g ・ショウガ 1片 ・ニンニク 1片 ・鷹の爪 1本 ・コーラ 70cc ・オリーブオイル(サラダ油でも大丈夫です。) 大さじ1 ・コショウ 適量 ・塩 適量 ・水 1/2カップ ・じゃがいも 1個 ・にんじん 1本 1.じゃがいもとにんじんは皮をむき、乱切りにしておく。 2.鶏もも肉を開いて軽く塩とコショウをまぶしておく。 3.ニンニクとショウガの皮をむき、薄くスライスし、鷹の爪は刻んで種を取り除いておく。...

【キャンプ道具】焚き火台を予算に合わせて選んでみよう
焚き火台は種類も豊富でメーカー仕様もたくさんあるので購入時に迷いがち。そんな時は予算で焚き火台を選んでみましょう。 2024/03/04 更新 5000円ならキャプテンスタッグ 焚き火台の予算を5000円くらいで考えているなら、キャプテンスタッグの「ヘキサステンレスファイアグリル」。 6角形の形をしているので、どの角度からも焚火にアプローチしやすくなっていて収納もコンパクトに収まります。 重量は3.8㎏と比較的重く感じますが焚き火用の網、バーベキュー用の網、収納ケースがセットでついているので値段のコスパ最高と感じる1台。 1万円ならロゴス 焚き火台を1万円くらいで考えているなら、ロゴスの「ピラミッドTAKIBI」。 付属のゴトクは差し込むように薪を立てかけられるので燃焼効率が上げることができ、ダッチオーブンのような重いものも載せられるのでとても便利です。 焚き火台本体の重さも2.2kgと持ち運びやすく、本体のほかにも専用のロストルと収納ケースも付いています。 2万円ならスノーピーク 「キャンプは焚き火がメイン」「焚き火台にこだわりたい」「かっこいい焚き火台を持っていたい」それならスノーピーク。 サイズはS/M/Lの3種類ありますが、Mサイズならセット販売(ベースプレート、炭床(ロストル)、収納ケース)は約2万円で販売しています。 唯一のデメリットといえば焚火台本体の重さ。他メーカーの焚火台は2kg台が多い中でこの焚火台はMサイズで3.5kgと若干重め。 持ち運びには少し苦労しますが、オールステンレスで仕上げた素材はデザイン・耐久性の両方から見ても間違いなく一生ものです。 最も高い焚き火台は? 現在で最も高い焚火台を販売しているのは、ロゴスの「ピラミッドマスター」で54000円。 本体の構造がステンレスの板をスリッドに差し込むタイプになっていて、バラすと板のみになるので、収納サイズが51×51×2cmと超薄型収納を実現しています。 そして、ステンレス素材の板を通常の焚火台の3倍の厚みにしているので、かなり高い耐久性を実現しています。 重さが「9.6㎏」とこちらでも高い耐久性が感じられます。高価格に相応しいハイスペック&ハイパフォーマンスの1台。 まとめ【キャンプ道具】焚き火台を予算に合わせて選んでみよう 以上をまとめると、 5000円なら「キャプテンスタッグ」10000円なら「ロゴス」20000円なら「スノーピーク」1番高い焚き火台はロゴスの「ピラミッドマスター」です。 焚き火台の購入に迷ったら予算で選んでみましょう。
【キャンプ道具】焚き火台を予算に合わせて選んでみよう
焚き火台は種類も豊富でメーカー仕様もたくさんあるので購入時に迷いがち。そんな時は予算で焚き火台を選んでみましょう。 2024/03/04 更新 5000円ならキャプテンスタッグ 焚き火台の予算を5000円くらいで考えているなら、キャプテンスタッグの「ヘキサステンレスファイアグリル」。 6角形の形をしているので、どの角度からも焚火にアプローチしやすくなっていて収納もコンパクトに収まります。 重量は3.8㎏と比較的重く感じますが焚き火用の網、バーベキュー用の網、収納ケースがセットでついているので値段のコスパ最高と感じる1台。 1万円ならロゴス 焚き火台を1万円くらいで考えているなら、ロゴスの「ピラミッドTAKIBI」。 付属のゴトクは差し込むように薪を立てかけられるので燃焼効率が上げることができ、ダッチオーブンのような重いものも載せられるのでとても便利です。 焚き火台本体の重さも2.2kgと持ち運びやすく、本体のほかにも専用のロストルと収納ケースも付いています。 2万円ならスノーピーク 「キャンプは焚き火がメイン」「焚き火台にこだわりたい」「かっこいい焚き火台を持っていたい」それならスノーピーク。 サイズはS/M/Lの3種類ありますが、Mサイズならセット販売(ベースプレート、炭床(ロストル)、収納ケース)は約2万円で販売しています。 唯一のデメリットといえば焚火台本体の重さ。他メーカーの焚火台は2kg台が多い中でこの焚火台はMサイズで3.5kgと若干重め。 持ち運びには少し苦労しますが、オールステンレスで仕上げた素材はデザイン・耐久性の両方から見ても間違いなく一生ものです。 最も高い焚き火台は? 現在で最も高い焚火台を販売しているのは、ロゴスの「ピラミッドマスター」で54000円。 本体の構造がステンレスの板をスリッドに差し込むタイプになっていて、バラすと板のみになるので、収納サイズが51×51×2cmと超薄型収納を実現しています。 そして、ステンレス素材の板を通常の焚火台の3倍の厚みにしているので、かなり高い耐久性を実現しています。 重さが「9.6㎏」とこちらでも高い耐久性が感じられます。高価格に相応しいハイスペック&ハイパフォーマンスの1台。 まとめ【キャンプ道具】焚き火台を予算に合わせて選んでみよう 以上をまとめると、 5000円なら「キャプテンスタッグ」10000円なら「ロゴス」20000円なら「スノーピーク」1番高い焚き火台はロゴスの「ピラミッドマスター」です。 焚き火台の購入に迷ったら予算で選んでみましょう。

「キャンプ道具がなくてもOK」なコテージの魅力と注意点
キャンプ道具を持たなくても、気軽にキャンプ体験できる方法の1つに「コテージ」があります。 コテージには宿泊するための設備が一通り揃っており、手軽に別荘気分を味わえるキャンプとして人気が高まっています。 さらに天候に左右されることもなくテント設営などの手間もかからないため、乳幼児を抱えた人や高齢者など幅広い世代から人気があります。 2024/03/05 更新 コテージとバンガローの違いは? コテージに似た建物でバンガローがありますが、コテージは生活道具の揃った山小屋的な宿泊施設に対して、バンガローは生活道具がなく照明とコンセントのみ付いている「建物だけ」の施設になるので利用する場合はキッチンツールや寝袋などある程度のキャンプ道具が必要になります。 したがって ・コテージは「普段の生活様式に近い感覚」でキャンプ体験ができる ・バンガローは「より自然に近い感覚」でキャンプ体験ができる が2つの違いになります。 コテージの注意点は? 事前に設備の確認をしなければいけない コテージは予約をする前に、どんな設備が付いているか確認をするのが大事です。とくにアメニティなど有無を確認して、持ち込みが必要なものがあれば持参しましょう。 料金が高い テントは無料で使えるキャンプ場もありますが、コテージは建物をまるまる一棟借りるのでその分料金も高くなってしまいます。 したがってキャンプをしたいけど道具を揃えるのが面倒な方や、キャンプ道具を揃えたいけど保管場所に困っている方はコテージの利用をおすすめしますが、コテージに払うお金がもったいないと考える方はキャンプの道具集めにお金を使うことをおすすめします。 コテージの魅力は? 天候に左右されない 通常のキャンプは天候に左右されやすいのが難点の1つ。雨の日にテントを設営すれば服がずぶ濡れになったり、寝るときは雨音がうるさくて眠れなかったりなど初心者にはハードルが高く感じることもあります。 しかし、コテージは雨の日でも設営で濡れることもなく、夜も壁に囲まれているので安心して眠れます。雨の降りやすい季節にキャンプをするならコテージがおすすめです。 冬キャンプデビューはコテージからでも◎ 冬のキャンプは暖房設備の準備や防寒対策など、高額なキャンプ道具と経験が求められるので、自信のない方はコテージで冬キャンプを始めるのも良いと思います。 例えば、群馬県にある「つくつく村」のコテージは外観が北欧風と南仏風の2種類のコテージがあり、内装は温もりのある木造づくりで暖炉が付いています。 このようにコテージには暖炉やエアコンなど暖房設備が整っている場所もあるので、快適な冬キャンプができるコテージを探してみるのも良いと思います。 他人を気にしなくても良い コテージはホテルや民宿と違い一棟借り。なので人の気配を気にする心配がなく、自然の中で木漏れ日や鳥の鳴き声を間近で感じることができます。喧騒を忘れて静かな時間を過ごしたい方にはとくにおすすめ。 最大で20人以上収容できるコテージも コテージには1人〜最大で20人以上も収容できる施設もあります。家族や友人などの少人数からサークルやグループ活動にも利用できるので、キャンプ体験をしてみたい人を集めてみるのも◎。 まとめ)「キャンプ道具がなくてもOK」なコテージの魅力と注意点...
「キャンプ道具がなくてもOK」なコテージの魅力と注意点
キャンプ道具を持たなくても、気軽にキャンプ体験できる方法の1つに「コテージ」があります。 コテージには宿泊するための設備が一通り揃っており、手軽に別荘気分を味わえるキャンプとして人気が高まっています。 さらに天候に左右されることもなくテント設営などの手間もかからないため、乳幼児を抱えた人や高齢者など幅広い世代から人気があります。 2024/03/05 更新 コテージとバンガローの違いは? コテージに似た建物でバンガローがありますが、コテージは生活道具の揃った山小屋的な宿泊施設に対して、バンガローは生活道具がなく照明とコンセントのみ付いている「建物だけ」の施設になるので利用する場合はキッチンツールや寝袋などある程度のキャンプ道具が必要になります。 したがって ・コテージは「普段の生活様式に近い感覚」でキャンプ体験ができる ・バンガローは「より自然に近い感覚」でキャンプ体験ができる が2つの違いになります。 コテージの注意点は? 事前に設備の確認をしなければいけない コテージは予約をする前に、どんな設備が付いているか確認をするのが大事です。とくにアメニティなど有無を確認して、持ち込みが必要なものがあれば持参しましょう。 料金が高い テントは無料で使えるキャンプ場もありますが、コテージは建物をまるまる一棟借りるのでその分料金も高くなってしまいます。 したがってキャンプをしたいけど道具を揃えるのが面倒な方や、キャンプ道具を揃えたいけど保管場所に困っている方はコテージの利用をおすすめしますが、コテージに払うお金がもったいないと考える方はキャンプの道具集めにお金を使うことをおすすめします。 コテージの魅力は? 天候に左右されない 通常のキャンプは天候に左右されやすいのが難点の1つ。雨の日にテントを設営すれば服がずぶ濡れになったり、寝るときは雨音がうるさくて眠れなかったりなど初心者にはハードルが高く感じることもあります。 しかし、コテージは雨の日でも設営で濡れることもなく、夜も壁に囲まれているので安心して眠れます。雨の降りやすい季節にキャンプをするならコテージがおすすめです。 冬キャンプデビューはコテージからでも◎ 冬のキャンプは暖房設備の準備や防寒対策など、高額なキャンプ道具と経験が求められるので、自信のない方はコテージで冬キャンプを始めるのも良いと思います。 例えば、群馬県にある「つくつく村」のコテージは外観が北欧風と南仏風の2種類のコテージがあり、内装は温もりのある木造づくりで暖炉が付いています。 このようにコテージには暖炉やエアコンなど暖房設備が整っている場所もあるので、快適な冬キャンプができるコテージを探してみるのも良いと思います。 他人を気にしなくても良い コテージはホテルや民宿と違い一棟借り。なので人の気配を気にする心配がなく、自然の中で木漏れ日や鳥の鳴き声を間近で感じることができます。喧騒を忘れて静かな時間を過ごしたい方にはとくにおすすめ。 最大で20人以上収容できるコテージも コテージには1人〜最大で20人以上も収容できる施設もあります。家族や友人などの少人数からサークルやグループ活動にも利用できるので、キャンプ体験をしてみたい人を集めてみるのも◎。 まとめ)「キャンプ道具がなくてもOK」なコテージの魅力と注意点...

冬キャンプをしたいならまずはグランピングを体験するべき2つの理由
2024/03/05 更新 グランピングとは? グランピングとは、グラマー(優雅・魅力的)とキャンピング(野営)を合わせた造語です。 キャンプ道具を持っていない人でも、設備の揃った場所で優雅にアウトドア体験ができる新しいキャンプスタイルとして近年需要が高まっています。 グランピングとキャンプの違いは? グランピングとキャンプの大きな違いは、グランピングは道具を準備せずにキャンプ体験ができるところ。 キャンプは基本的に道具から食材まで全て自分で準備をして、キャンプ場に向かいます。しかし、道具の買い忘れやキャンプの情報不足から起きるトラブルなど、初心者にとっては少しハードルの高さを感じてしまうもの。 グランピングはそんな細かいことを気にする必要もなく、リゾートホテルに泊まるような気分でキャンプの魅力を存分に楽しめます。 グランピングは、あらかじめ準備されている超大型のテントやコテージ、トレーラーハウスを使った様々な宿泊施設の演出があり、食材や炭の準備も専属のスタッフにお任せで面倒な後片付けも不要など、文字通りグラマーな体験ができます。 さらに、道具の設営や撤収作業もないので、通常のキャンパーよりも長くキャンプ時間を満喫できます。キャンプをやってみたいけど面倒なことをしたくないなら、まずはグランピングからキャンプ体験をしてみましょう。 冬にグランピングをするべき2つの理由とは? 危険が少ない 冬にグランピングをするべき1つめの理由は「危険が少ない」から。 冬キャンプはベテランキャンパーでも危険の多い時期となっており、乾燥による火災や暖気を逃さないためにテントを密室にして、一酸化炭素中毒になるトラブルなど冬の特徴的な事故が増加します。 このようなトラブルから身を守るには、豊富な知識と経験が必要になってくるので冬キャンプをしたいなら、まずは設備の整っているグランピングで冬キャンプの魅力を体験するべきだと思います。 費用が安い 冬にグランピングをするべき2つめの理由は「高額な防寒対策の道具を揃えなくて良い」から。 冬キャンプは防寒対策のために、1人あたり10万円程度かかる高いキャンプ道具(寝袋・マット・コット・防寒着・ストーブなど)を揃えなくてはいけませんが、 「キャンプを始めるのにそんなに費用をかけられない」 「冬用の高いキャンプ道具は買わずに安い道具で済まそう」 と考えて冬キャンプに行って寒さに耐えきれずにやめてしまうキャンパーがいます。 このように、せっかくの冬キャンプに興味を持ったのに魅力を知れないままキャンプを諦めてしまうのはとても残念に感じます。 グランピングなら高いキャンプ道具を揃えなくても「ストーブの温もり」「空気の澄んだキレイな冬空」「冬の炎の美しさ」など、冬キャンプでしか味わえない特別な魅力を満喫できるので、費用を抑えたい方はグランピングから始めてみるべきだと思います。 まとめ)冬キャンプをしたいならまずはグランピングにするべき2つの理由 以上をまとめると、 冬のキャンプはグランピングにするべき理由は2つ 1つめは「危険が少ない」 2つめは「費用が安い」 です。...
冬キャンプをしたいならまずはグランピングを体験するべき2つの理由
2024/03/05 更新 グランピングとは? グランピングとは、グラマー(優雅・魅力的)とキャンピング(野営)を合わせた造語です。 キャンプ道具を持っていない人でも、設備の揃った場所で優雅にアウトドア体験ができる新しいキャンプスタイルとして近年需要が高まっています。 グランピングとキャンプの違いは? グランピングとキャンプの大きな違いは、グランピングは道具を準備せずにキャンプ体験ができるところ。 キャンプは基本的に道具から食材まで全て自分で準備をして、キャンプ場に向かいます。しかし、道具の買い忘れやキャンプの情報不足から起きるトラブルなど、初心者にとっては少しハードルの高さを感じてしまうもの。 グランピングはそんな細かいことを気にする必要もなく、リゾートホテルに泊まるような気分でキャンプの魅力を存分に楽しめます。 グランピングは、あらかじめ準備されている超大型のテントやコテージ、トレーラーハウスを使った様々な宿泊施設の演出があり、食材や炭の準備も専属のスタッフにお任せで面倒な後片付けも不要など、文字通りグラマーな体験ができます。 さらに、道具の設営や撤収作業もないので、通常のキャンパーよりも長くキャンプ時間を満喫できます。キャンプをやってみたいけど面倒なことをしたくないなら、まずはグランピングからキャンプ体験をしてみましょう。 冬にグランピングをするべき2つの理由とは? 危険が少ない 冬にグランピングをするべき1つめの理由は「危険が少ない」から。 冬キャンプはベテランキャンパーでも危険の多い時期となっており、乾燥による火災や暖気を逃さないためにテントを密室にして、一酸化炭素中毒になるトラブルなど冬の特徴的な事故が増加します。 このようなトラブルから身を守るには、豊富な知識と経験が必要になってくるので冬キャンプをしたいなら、まずは設備の整っているグランピングで冬キャンプの魅力を体験するべきだと思います。 費用が安い 冬にグランピングをするべき2つめの理由は「高額な防寒対策の道具を揃えなくて良い」から。 冬キャンプは防寒対策のために、1人あたり10万円程度かかる高いキャンプ道具(寝袋・マット・コット・防寒着・ストーブなど)を揃えなくてはいけませんが、 「キャンプを始めるのにそんなに費用をかけられない」 「冬用の高いキャンプ道具は買わずに安い道具で済まそう」 と考えて冬キャンプに行って寒さに耐えきれずにやめてしまうキャンパーがいます。 このように、せっかくの冬キャンプに興味を持ったのに魅力を知れないままキャンプを諦めてしまうのはとても残念に感じます。 グランピングなら高いキャンプ道具を揃えなくても「ストーブの温もり」「空気の澄んだキレイな冬空」「冬の炎の美しさ」など、冬キャンプでしか味わえない特別な魅力を満喫できるので、費用を抑えたい方はグランピングから始めてみるべきだと思います。 まとめ)冬キャンプをしたいならまずはグランピングにするべき2つの理由 以上をまとめると、 冬のキャンプはグランピングにするべき理由は2つ 1つめは「危険が少ない」 2つめは「費用が安い」 です。...

冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイント
冬キャンプは、厳しい寒さの中で快適に過ごすための道具選びがとても重要になります。 その中で、最も重要になる道具の1つ「テント選び4つのポイント」を解説します。 2024/03/12 更新 1.選ぶなら広いテントを 冬キャンプのテント選び1つの目のポイントは「広いテントを選ぶ」です。 冬のキャンプは夏と比べて衣類や毛布、暖房器具やポータブル電源など防寒対策のかさばる道具が多く、車に積むときもすぐに車内は満タンになってしまうくらい荷物が増えるので、居住スペースを確保するためにも広いテントにしましょう。 そして、冬キャンプは暖かいテントの中で過ごすことが多いので、居住スペースが狭いとストレスを感じてしまいます。 狭いテントでストーブを使用すると、火災の原因にもなるので冬キャンプをするなら広いテントを選びましょう。 2.結露対策できるテントを選ぶ テント選び2つ目のポイントは「結露対策のできるテントを選ぶ」です。 冬のキャンプはテント内でストーブなどの暖房器具を使用すると、外側との寒暖差からテントの内側に結露が発生し、テントの内壁に貼り付いて雫となって下に落ちてきて端に置いていたキャンプ道具や服を濡らしてしまいます。 そんな結露を防ぐ対策には二重構造のテントを選びましょう。二重構造のテントとは別名「ダブルウォールテント」と呼ばれ、居住空間のインナーテントの上に防水用のフライシートを張ることで空気の層を作り、外気との寒暖差を減らすことができます。 最近販売されているテントは、このダブルウォールタイプのテントが主流になっているのでチェックしてみてください。 3.スカート付きテントを選ぶ テント選び3つめのポイントは「スカート付きのテントを選ぶ」です。 スカートとはテント(フライシート)下部の地面と接するところについているヒダ状シートのことで、スカートが地面に接地することでテントのすきま風を防いだり暖気が逃げるのを防ぐ役割があり、寒冷地のキャンプであるのとないのでは大きな差が出ます。 雪の降る地域では、スカートの上に雪を被せてすきま風を防いだりもできます。基本的には3シーズン(春・夏・秋)用のテントよりも、寒冷地(冬)用のテントに装備されている場合が多いのでチェックしてみましょう。 4.ベンチレーション付きのテントを選ぶ テントの選び方4つめのポイントは「ベンチレーションのついたテントを選ぶ」です。ベンチレーションとは換気装置のことで、テントには中の空気を入れ替えるための換気口がついているものがあります。 換気口といっても機械ではなくファスナーでテントの一部を開け閉めできる装備になっており、グレードの高いテントは換気口がメッシュ構造になっていて虫などの侵入も防げるようになっています。 冬キャンプでは暖気を逃さないために閉めっきりにしますが、閉めきったテントでストーブなどの火器を長時間使用すると酸素が減り一酸化炭素中毒になる危険があるので、ベンチレーションで効率良く空気の入れ替えをして一酸化炭素中毒を防止しましょう。 まとめ)冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイント 以上をまとめると、冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイントとは、 広いテントを選ぼう 結露対策できるテントを選ぼう スカート付きのテントを選ぼう ベンチレーションのついたテントを選ぼう です。 快適なテントを選んで冬キャンプを楽しみましょう。
冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイント
冬キャンプは、厳しい寒さの中で快適に過ごすための道具選びがとても重要になります。 その中で、最も重要になる道具の1つ「テント選び4つのポイント」を解説します。 2024/03/12 更新 1.選ぶなら広いテントを 冬キャンプのテント選び1つの目のポイントは「広いテントを選ぶ」です。 冬のキャンプは夏と比べて衣類や毛布、暖房器具やポータブル電源など防寒対策のかさばる道具が多く、車に積むときもすぐに車内は満タンになってしまうくらい荷物が増えるので、居住スペースを確保するためにも広いテントにしましょう。 そして、冬キャンプは暖かいテントの中で過ごすことが多いので、居住スペースが狭いとストレスを感じてしまいます。 狭いテントでストーブを使用すると、火災の原因にもなるので冬キャンプをするなら広いテントを選びましょう。 2.結露対策できるテントを選ぶ テント選び2つ目のポイントは「結露対策のできるテントを選ぶ」です。 冬のキャンプはテント内でストーブなどの暖房器具を使用すると、外側との寒暖差からテントの内側に結露が発生し、テントの内壁に貼り付いて雫となって下に落ちてきて端に置いていたキャンプ道具や服を濡らしてしまいます。 そんな結露を防ぐ対策には二重構造のテントを選びましょう。二重構造のテントとは別名「ダブルウォールテント」と呼ばれ、居住空間のインナーテントの上に防水用のフライシートを張ることで空気の層を作り、外気との寒暖差を減らすことができます。 最近販売されているテントは、このダブルウォールタイプのテントが主流になっているのでチェックしてみてください。 3.スカート付きテントを選ぶ テント選び3つめのポイントは「スカート付きのテントを選ぶ」です。 スカートとはテント(フライシート)下部の地面と接するところについているヒダ状シートのことで、スカートが地面に接地することでテントのすきま風を防いだり暖気が逃げるのを防ぐ役割があり、寒冷地のキャンプであるのとないのでは大きな差が出ます。 雪の降る地域では、スカートの上に雪を被せてすきま風を防いだりもできます。基本的には3シーズン(春・夏・秋)用のテントよりも、寒冷地(冬)用のテントに装備されている場合が多いのでチェックしてみましょう。 4.ベンチレーション付きのテントを選ぶ テントの選び方4つめのポイントは「ベンチレーションのついたテントを選ぶ」です。ベンチレーションとは換気装置のことで、テントには中の空気を入れ替えるための換気口がついているものがあります。 換気口といっても機械ではなくファスナーでテントの一部を開け閉めできる装備になっており、グレードの高いテントは換気口がメッシュ構造になっていて虫などの侵入も防げるようになっています。 冬キャンプでは暖気を逃さないために閉めっきりにしますが、閉めきったテントでストーブなどの火器を長時間使用すると酸素が減り一酸化炭素中毒になる危険があるので、ベンチレーションで効率良く空気の入れ替えをして一酸化炭素中毒を防止しましょう。 まとめ)冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイント 以上をまとめると、冬キャンプのテント選びで重要な4つのポイントとは、 広いテントを選ぼう 結露対策できるテントを選ぼう スカート付きのテントを選ぼう ベンチレーションのついたテントを選ぼう です。 快適なテントを選んで冬キャンプを楽しみましょう。

冬キャンプに持っていくストーブの選び方について詳しく解説
冬キャンプの持って行くべき必須ギアの1つにストーブがありますが、冬キャンプのストーブには薪ストーブと石油ストーブの2種類があります。 この2つのストーブの違いと特徴を理解して、自分に合ったストーブ選びをしましょう。 2024/03/05 更新 薪ストーブとは 薪ストーブとは薪を燃料に使うストーブです。薪は一束500~800円程度で購入できますが、無料で使えるキャンプ場もあり燃料を持ち運んだり燃料代をかけずにストーブを使える利点があります。 薪ストーブ本体の形状は様々で、中には組み立て式や折り畳めるタイプもあり、携帯性に優れていることから持ち運びに困難な山奥や荷物を軽くしたいキャンパーに人気があります。 しかし、他の暖房器具と比べて一酸化炭素を多く排出することや火力の調整が難しく、火事の危険も高まるなどキャンパーとしてある程度の経験と練度が求められる一面もあります。 キャンプが初めての方はすぐに薪ストーブは買わずに、キャンプにある程度慣れてからの使用をおすすめします。 石油ストーブとは 石油ストーブとは、ガソリンスタンドやホームセンターで販売されている灯油を燃料に使うストーブです。 とその前に、石油ストーブと灯油ストーブの違いを説明します。そもそも石油とは炭素混合物液体の総称ですが精製段階で重油、軽油、ガソリン、灯油などに分けられ動力燃料として用いられます。 ちなみに発掘して未精製の状態は原油です。日本では室内で灯油を使う暖房器具のことを灯油ストーブとは呼ばずに、石油ストーブという名前の方が広く認知されているので、以下では石油ストーブで統一させていただきます。 石油ストーブには大きく分けて2つのタイプがあり、1つは四角い形状をした反射式、2つめは円柱の形状をした対流式です。 反射板を使い遠赤外線効果で正面と上部を温める反射式に対して、対流式は冷たい冷気を暖気に変えて対流させながら360℃方向から温まることができます。 住宅と比べ、狭い環境で効率よく暖をとりたい冬のキャンプはどちらかと言うと対流式の方が人気があるようですが、対流式は価格が高く反射式の倍近い予算が必要になります。 冬キャンプで反射式ストーブは使えるの? 反射式のストーブは冬のキャンプにも使えますがいくつか注意が必要です。 1つめは、主に自宅での使用をメインとする反射式ストーブは補給効率をよくするためにタンクが備わっていますが、タンクの燃料を満タンにして持っていくと使いきれない可能性が高いので、必要な分だけ灯油を用意するのが良いと思います。 2つめは、反射式のストーブは横揺れに弱く燃料が入っているとすぐにこぼれます。車内でこぼれてしまうと、たちまち臭いが充満して気分が悪くなってしまうので、持ち運ぶときはタンク内の燃料を空にして灯油は専用のポリタンクに入れて持っていきましょう。 ストーブ本体は、タンクを取り外すと下の方に灯油を溜めておく場所があればそこもスポイトでとれるだけとっておきましょう。とりきれない場合はタンクと本体のジョイント部分にタオルなどで塞いでおくのも良いと思います。 さらにストーブ本体の下に受け皿を用意しておけば、こぼれてしまった時でも車内に灯油が染みついてしまうのを防ぐことができます。 車に積むときにストーブのカバーがあるといいのですが、メーカーではほとんど市販されていないので、自作をするか代わりになるようなものを見つけておくと良いと思います。 まとめ)冬キャンプに持っていくストーブの選び方について詳しく解説 以上をまとめると冬キャンプのストーブは、 薪ストーブと石油ストーブの2種類 薪ストーブはある程度のキャンプ経験と練度が必要 石油ストーブは反射式と対流式と2つのタイプがある おすすめは対流式。でも値段が高い 反射式は値段が安いけど準備が面倒...
冬キャンプに持っていくストーブの選び方について詳しく解説
冬キャンプの持って行くべき必須ギアの1つにストーブがありますが、冬キャンプのストーブには薪ストーブと石油ストーブの2種類があります。 この2つのストーブの違いと特徴を理解して、自分に合ったストーブ選びをしましょう。 2024/03/05 更新 薪ストーブとは 薪ストーブとは薪を燃料に使うストーブです。薪は一束500~800円程度で購入できますが、無料で使えるキャンプ場もあり燃料を持ち運んだり燃料代をかけずにストーブを使える利点があります。 薪ストーブ本体の形状は様々で、中には組み立て式や折り畳めるタイプもあり、携帯性に優れていることから持ち運びに困難な山奥や荷物を軽くしたいキャンパーに人気があります。 しかし、他の暖房器具と比べて一酸化炭素を多く排出することや火力の調整が難しく、火事の危険も高まるなどキャンパーとしてある程度の経験と練度が求められる一面もあります。 キャンプが初めての方はすぐに薪ストーブは買わずに、キャンプにある程度慣れてからの使用をおすすめします。 石油ストーブとは 石油ストーブとは、ガソリンスタンドやホームセンターで販売されている灯油を燃料に使うストーブです。 とその前に、石油ストーブと灯油ストーブの違いを説明します。そもそも石油とは炭素混合物液体の総称ですが精製段階で重油、軽油、ガソリン、灯油などに分けられ動力燃料として用いられます。 ちなみに発掘して未精製の状態は原油です。日本では室内で灯油を使う暖房器具のことを灯油ストーブとは呼ばずに、石油ストーブという名前の方が広く認知されているので、以下では石油ストーブで統一させていただきます。 石油ストーブには大きく分けて2つのタイプがあり、1つは四角い形状をした反射式、2つめは円柱の形状をした対流式です。 反射板を使い遠赤外線効果で正面と上部を温める反射式に対して、対流式は冷たい冷気を暖気に変えて対流させながら360℃方向から温まることができます。 住宅と比べ、狭い環境で効率よく暖をとりたい冬のキャンプはどちらかと言うと対流式の方が人気があるようですが、対流式は価格が高く反射式の倍近い予算が必要になります。 冬キャンプで反射式ストーブは使えるの? 反射式のストーブは冬のキャンプにも使えますがいくつか注意が必要です。 1つめは、主に自宅での使用をメインとする反射式ストーブは補給効率をよくするためにタンクが備わっていますが、タンクの燃料を満タンにして持っていくと使いきれない可能性が高いので、必要な分だけ灯油を用意するのが良いと思います。 2つめは、反射式のストーブは横揺れに弱く燃料が入っているとすぐにこぼれます。車内でこぼれてしまうと、たちまち臭いが充満して気分が悪くなってしまうので、持ち運ぶときはタンク内の燃料を空にして灯油は専用のポリタンクに入れて持っていきましょう。 ストーブ本体は、タンクを取り外すと下の方に灯油を溜めておく場所があればそこもスポイトでとれるだけとっておきましょう。とりきれない場合はタンクと本体のジョイント部分にタオルなどで塞いでおくのも良いと思います。 さらにストーブ本体の下に受け皿を用意しておけば、こぼれてしまった時でも車内に灯油が染みついてしまうのを防ぐことができます。 車に積むときにストーブのカバーがあるといいのですが、メーカーではほとんど市販されていないので、自作をするか代わりになるようなものを見つけておくと良いと思います。 まとめ)冬キャンプに持っていくストーブの選び方について詳しく解説 以上をまとめると冬キャンプのストーブは、 薪ストーブと石油ストーブの2種類 薪ストーブはある程度のキャンプ経験と練度が必要 石油ストーブは反射式と対流式と2つのタイプがある おすすめは対流式。でも値段が高い 反射式は値段が安いけど準備が面倒...